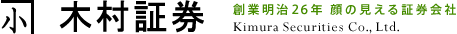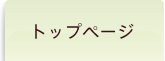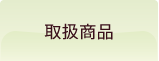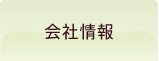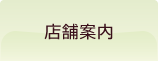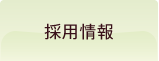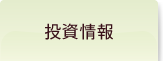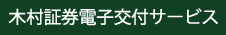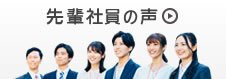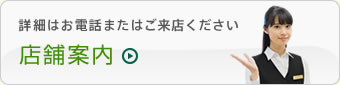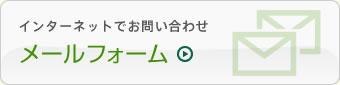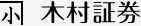未解決の少子化問題 (2025年7月版)
関税交渉の決着を前に、株価は4月のトランプ大統領の相互関税発表前の水準を回復した。日本株は半導体や防衛関連を中心に上昇し、関税交渉の行方を見守りつつ、上値を狙う動きを見せている。
先月公表された人口動態統計で、2024年の日本人出生数は統計のある1899年以降で初めて70万人を割り込み(=68万6,061人)、合計特殊出生率(=1.15)は過去最低を更新した。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(出生中位・死亡中位)は、経済成長や社会保障の前提とされる基本シナリオだが、24年の数値は低位のシナリオに近く、中位想定に比べて15年早い。死亡数は160万5,298人、出生数と死亡数の差となる自然減は91万9,237人で、ともに過去最多となり、昨年1年間で香川県の人口と同規模の人口減少となった。たびたび取り上げる少子化と多死社会問題は、未解決のまま日本経済に暗い影を落し始めている。
少子化の要因には、一番に結婚の減少がある。一般的な理由として、実質賃金の伸び悩みを背景とした、家族を養う経済的負担を考えることでの婚姻意欲の低下があげられる。また、就労を要因とした地域ごとの男女人口の分布バランスの悪化についても指摘される。製造業中心とした地域では、男性人口の比率が高くなる傾向がある反面、若年女性は就労で大都市圏へ流出する傾向にあり、男性がパートナーとなる女性を見つけづらい状況が生じている。日本はかつてから、東京など大都市を中心に核家族世帯社会であったが、近年では地方にも核家族化の波が急速に進んでいる。核家族中心の社会的変化によって、子供に対する親からの結婚の働きかけが弱まるとともに、共働きや子供世代が新たな住宅を取得しなければならなくなる経済事情も、結婚へのハードルを高める要因となっている。
昨年、政府は骨太の方針で「経済・財政・社会保障の持続可能性を図るため、30年代以降に実質1%成長を続ける必要がある」とした。内閣府では60年度まで成長し続けるには、最終的に同出生率が1.64まで回復する必要があると試算しており、現在の出生率のままではマイナス成長が続くと推察される。今後、女性や高齢者の就労促進によって維持されてきた労働力人口も、少子化が続けば補いきれず、特に高齢化とともに医療・介護・運送業でのサービスの維持は困難となる可能性がある。
消費を下振れさせると同時に、社会保障制度の持続性についての心配する声も多い。医療・介護の給付費が年々増加する中、年金はマクロ経済スライドにより100年安心と謳われているが、厚生省が昨年公表した財政検証では、実質0%成長が続いた場合の基礎年金の給付水準調整は30年後まで続き、夫婦2人のモデル世帯の場合で所得代替率(現役世代の平均手取り収入額と比較した給付水準)は、29.6%下がると試算されている。これも70年の合計特殊出生率が1.36に回復することが前提で、0%成長かつ低位シナリオの1.13の場合では、65年度に4割近く下がる計算となる。
前国会で一度取り下げられた与党の年金制度改革法案は、3党の合意により成立した。修正案は、4年後に実施予定の年金財政検証において、マクロ経済スライドの調整期間の著しい差や、基礎年金給付水準の低下が見込まれる場合の調整措置が法案の付則として盛り込まれた。年金改革法案は、厚生年金の積立金を活用して基礎年金を底上げするもので、少子高齢化による年金制度の課題を解決する糸口として修正された。たとえば、就職氷河期により存在する非正規雇用者の低年金と、生活保護に陥ることを防止するために必要とされている。だが、基礎年金の財源は半分を税金で賄うこととなっており、底上げに伴う税財源の道筋は、4年後を見据えた課題と考えられる。かつて、現在の少子高齢化社会時代を迎えるまで、年金は胴上げ型(多くの現役世代で1人の高齢者を支える)から、騎馬戦型(3人程度の現役世代が1人の高齢者を支える)へ、そして肩車型(1人の高齢者が1人の現役世代を支える)への移行が揶揄されてきた。それが今や地方レベルでは、1人の現役世代が2人の高齢者を支える天秤棒型に近い状態への移行が迫ろうとしている。
個々の保険料負担が年々増加して、可処分所得が圧迫される状況が継続していては、消費にお金が回らない悪循環から当然のように、抜け出すことはできない。根幹にある人口問題に対し日本全体が真摯に向き合わなければ、国の存続にかかわる時が来てもおかしくない。
(戸谷 慈伸)