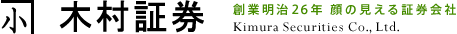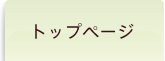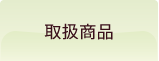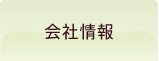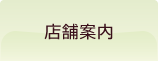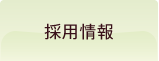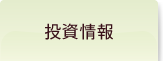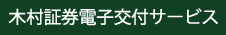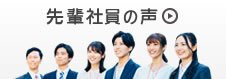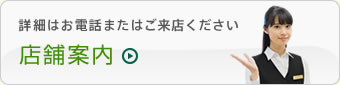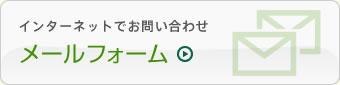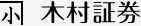株式市場展望 (2026年1月版)
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
昨年前半の株価は、米トランプ大統領の関税発動により、内外の経済や業績への影響を不安視し、軟調に推移した。後半は、関税合意と後の企業決算の堅調さを踏まえ、市場に安心感が広がった。10月には、高市首相誕生と予想以上の米国AI関連の堅牢さにより、騰勢を強めた日経平均株価は5万円を突破した。PER(株価収益率)から見ると現在の水準は割高と受け止める向きもあるが、市場が来期の業績を織り込み始めたこと踏まえれば、妥当な水準と考えられる。
今年は、十干十二支の丙午(ひのえうま)。丙は陽の火を表し、午も火の気を持つため、火の性質が二重に重なった強いエネルギーの年とされる。丙午は60年に一度の特別な年で、強いエネルギーが社会現象を起こすとして、1966年には出生率が大幅に低下して社会問題となった出来事がある。馬は速さや力強さ、情熱の象徴とされており、物事が急速に進展する傾向がある一方、持久力の面から走り続けられない限界も示唆される。
株式市場の干支格言では「午尻下がり」といわれ、勢いよく上昇するが、後半失速して尻すぼみになるとされる。事実、東証再開後から2024年までの75年間では、午年の平均騰落率は十二支中で唯一、マイナスを記録しており、過去6回の午年の前半と後半の平均でも、前半が+3.2%に対し後半が-7.8%と尻下がりの格言通りとなっている。
今年の相場を展望してみたい。まず、現在の株価が前述のように来期の企業業績を先取りしているとした場合、予想通りに達成できるか、あるいは下回る水準にとどまるかによって、株価の先行きは大きく居所を変えることとなる。そのため、株価の必須要件として業績見通し発表には常に注意を払いたい。
次に高市政権の経済政策、成長戦略である。今回、大胆な危機管理投資と成長投資による力強い経済成長を政策として掲げ、司令塔として日本成長戦略会議が立ち上げられた。AI・半導体、造船、量子コンピュータ、バイオ、航空・宇宙、サイバーセキュリティ、コンテンツなどの17項目を重点分野とし、官民連携での投資強化を目指すこととなる。もとより成長期待の高いAI・半導体や防衛分野は、政府の投資によって一段と拡大する期待が高まる。今年は、政権がめざす経済の持続的な成長戦略の真価が問われる試金石となる。現時点では、高市政権への期待感の先行が株価を押し上げる一因ともいえるだけに、反対勢力を抑え込み、期待に応えられるかが重要なカギとなる。政策の根底である成長投資による企業の稼ぐ力を強化することは、収益が上がれば税収増となり、積極財政を推進する原動力となる。実質賃金がプラスとなる賃上げを促すことも可能となり、それが大きなインフレ対策と考えられる。官民挙げた改革で稼ぐ力が向上すれば、企業の資本効率改善も期待され、ROE(自己資本利益率)の上昇が一段と進む可能性も高く、日本株の上昇余地は大きくなるとみられる。政権運営による民間支援の実施状況や、今後の政権支持率の推移には注意を払いたい。
金利の上昇傾向は、緩やかな景気回復により続くとみられる。長期金利(10年国債利回り)は、19年ぶりの2%台水準が予想され、日銀の利上げスタンスは続くとみられるが、ペース自体は慎重かつ緩やかなものと考えられる。ただ、積極財政が市場の懸念を過敏に誘発しうる点は注意しておきたい。
ドル円相場は、日米金利差が縮小する方向にはあるものの、昨年同様1ドル=150円台を中心とした動きが継続するとみられる。物価上昇を想定すれば、実質金利は依然としてマイナス水準となり、円買いは抑えられる。加えて、貿易収支やデジタル収支の赤字や対外直接投資の増加が続けば、実需面でも引き続き円売り要因が存在する。
米国は、FRB議長交代と中間選挙を控え、金利引き下げと追加減税による景気刺激策や、関税政策による一部製造業の国内回帰と海外企業の直接投資が期待されており、後半にむけて景況感回復が期待される。中国は、景気減速感のなか、不動産不況の終焉も見通せておらず、かつてのような力強さはない。ただ米国の追加関税発動の一部先送りや、グローバルサウス向け輸出により、景気下支えはされるだろう。ただ昨年末以降の日中関係の悪化の影響が、双方とも景気下押し要因になるかどうか現時点では不確実であり、状況を見守る必要がある。
以上を踏まえて今年の日経平均株価は、50,000円を基準に上値+7,500円、下値-5,000円近辺の推移と考えたい。波乱含みの乱高下に一喜一憂せず、勝ち馬に乗られる事をお祈りいたします。
(戸谷 慈伸)